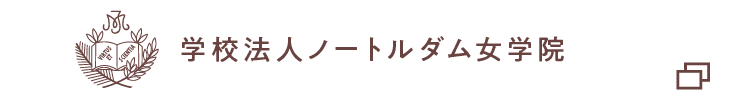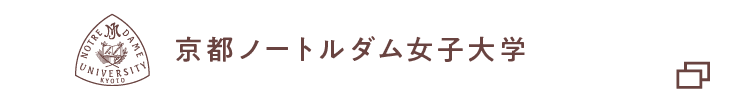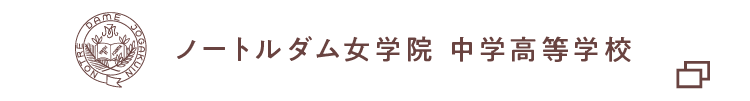出口の見えない長期の自宅生活
生徒の心と体の健康を見守りたい
緊急事態宣言の発出以降、「コロナ鬱」という言葉をよく耳にした。人との接触を避けるために自宅にこもる生活が長引く中で、体と心が悲鳴を上げ始める。大人社会でもそうした弊害が起きた。
今回のコロナ禍による中学・高校生の生活環境の変化は、大人以上に衝撃があった。終業式もできないままの休校、クラブ活動も完全ストップ。新学年になっても登校できず、不慣れなオンライン授業もスタート。友達とふざけあい笑いあったあたり前の日常が、こつ然と消えた。
そんな出口の見えない自宅生活を続けた生徒たちの心と体の健康を見守ったのが、教育相談室の黒田だ。
「平常時の私は、週3~4日程度、校舎3階にある教育相談室で、お昼休みと放課後の時間を使って生徒のあらゆる相談にのっています。私は非常勤ですが、教育相談室には私以外にもスクールカウンセラーが二人いますから、いつ相談に来てもらってもいい、何の話でもいい。生徒には、『勉強の仕方でもええし、友達関係でもええし、おうちのことでもええから、困ったことがあったら気軽に話しに来て』と伝えています。もちろん個別です」。
教育相談室を訪れる生徒には、1回の相談でスッキリして帰る生徒もいれば、定期的な相談を要する生徒もいる。休校期間中にかかわらず、教育相談室はそのいずれの生徒に対しても「オンラインのドア」を開けていた。
以前は、LD等通級指導教室の担任も
豊富な経験を、生徒の相談に活かす
ノートルダムに着任する以前の黒田は、京都市の公立校で、長年にわたって教論として勤務。さらにはLD等通級指導教室の担任として発達障害のある生徒の指導にもあたった。その経験は、いま生徒から寄せられるさまざまな相談に活かされている。
黒田は、経験を振り返りながら話す。
「正しくは、発達障害と鬱は異なります。発達障害は、脳の『発達の凸凹』から生じるもので可逆性はないとされており、『治す』のではなく『適応できる力をつける』ことを目的とします。一方の鬱は、急激な環境変化や過度のストレスなどで生じる心の病気で2次的なもの。これはいろんなアプローチで『治す』ことを目指します」。
「また、『発達の凸凹』があることは、決して特別なことではありません。それが極端なのか少しなのか、程度の差はあれ、誰もが抱えているものです。この相談室でも、以前こんな相談を受けました。“授業でディスカッションする場面になると、どうやって話し始めたらいいかわからへん”と。これ、誰でも少なからず感じますよね、だから全然特別じゃない。多くの人の場合、その事態を解決する術を時間をかけて体得し、経験知に変えながら適応していく。私がしている相談は、そうした経験をサポートすることです」。
「たとえば、きっかけづくりの言葉ってあるじゃないですか。“ちょっと聞いてもいい?”とか、“私、次にしゃべってもいいかな”とか、それをロールプレイする。私が友達役になって、生徒はそのきっかけづくりの言葉を練習する。練習したら実際の授業で試してみる。次に相談に来たときには、どうやった?と聞いてみる。うまいこといったなら一緒に喜び、次の困っていることの解決策を考える。そんなちょっとしたこと、一つひとつの“できるようになる”を積み重ねながら、日常生活のあちこちに潜む“困った事態”に適応できる力をつけていくんです」。
休校期間中、普段から定期的に相談室を訪れている生徒には、Google Classroomにひとりずつ部屋をつくり、週1回程度Google Meetで教員相談を続けた。急激に環境が変わったために予期せず心に変調をきたしてしまった生徒の相談にものった。
たとえ学校は閉じていたとしても、教育相談室の「オンラインのドア」はいつもと変わりなく開けておく。それが黒田の意志だった。
教育相談室と体育科で企画した自主活動
「美活部」でストレスのない自宅生活を
もう一つ、休校期間中に黒田が担った大きな役割がある。「美活部」の活動だ。黒田が体育科の三井と村田(亜)に声を掛けて始まった。自宅でできる簡単なストレッチやリラックスできる運動を映像にまとめ、3人それぞれに毎週1回定期的に配信した。体育の授業としてではない。生徒とその家族を心と体の健康維持してもらうための自主活動だ。
「実は私は、教育キネシオロジー・ブレインジムのインストラクターでもあるんです。軽く体を動かすことで脳を活性化させ、ポジティブになりましょう、という運動です。生徒に家での様子を聞けば、指導に従うまじめな生徒ほど、外出もきちんと自粛していました。そうすると、コロナ太りも起きるし、筋力も落ちる。また、3カ月間家族と一日中ずっと一緒にいるわけです。ただでさえ親に対して反発しがちな思春期、親をうっとうしく感じたり多少は大きな声も出したりする。そんなイラついた毎日だとお互いに大変でしょ。心が落ち込んでしまう前に予防してあげたかったんです。気分転換できたり、家族で一緒にできたりする運動メニューをつくって、動画で配信しようとなりました」。
企画、撮影、編集からBGMもテロップも
初めての映像制作でもまずまずの完成度
動画は、黒田が8本制作したのをはじめ、合計16本制作した。
各自が運動メニューを考え、自分で撮影して、1本は約7分程度に収まるように映像を切り貼りして尺を調整・編集、BGMもつけた。また、伝えたいことは文字もあったほうがわかりやすいからとテロップも入れた。
「映像の編集・制作には、iMovieを使いました。もちろん初めての挑戦です。最初は撮影から完成まで、1本つくるのに3時間ぐらいはかかったでしょうか、結構てこずりました。が、いろんな編集作業も慣れてくると意外にサクサクできるようになります。とはいえ、運動メニューから考えるので、毎週1本ペースで制作するのはプレッシャーでした(笑)。それよりも不安だったのは、これだけ手を掛けながらも本当に生徒の役に立っているのか?そちらの方が気になりました」。
学校が再開され、美活部の活動はいったん終えた。生徒からは「先生、家でお母さんとやったよ」という声も多くもらえた。それだけでも十分だったが、黒田は新たな可能性も感じ始めている。
「映像をつくってライブラリー化しておけば、繰り返し何度でも、好きな時間にやってもらえるんですよ。今後は、顔つき合わせたリアルな相談の場と、映像を使った手軽な健康づくりとストレス解消の場、そんな組み合わせ方も考えられると思います」。