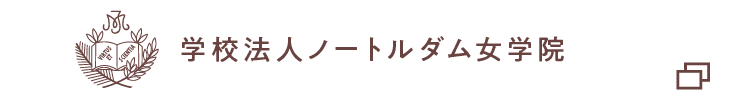ノートルダム女学院教育の核をなす
海外プログラムのすべてが中止に
ノートルダム女学院の海外プログラムは、その目的も渡航先もさまざまだ。プレップ総合コース、グローバル英語コース、STE@M探究コースのいずれにも、正課授業としての海外プログラムが設けられているだけでなく、コースを超えた課外授業の特別プログラムも用意されている。
2020年度(2020年4月以降)は、これらの海外プログラムのすべてを中止した。また、出ていくだけではなく、海外からの留学・研修生を受け入れるプログラムもすべて中止せざるを得なかった。
■ ノートルダム女学院のおもな海外研修・留学<正課>
海外プログラムは、
学びを深く豊かにする「きっかけの場」
いずれのプログラムも、長くても数カ月間(※個人手配の留学プログラムには1年間のコースもある)、短ければ1週間程度だ。もちろん、この限られた期間では、現地の文化や価値観のすべてを理解することはできない。あるいは誰もが飛躍的に語学を上達させて帰ってくるというものでもない。
それでも、これらのプログラムを実施する価値は大きい。プログラムの狙いは、これらの体験を通じて、異文化の中で直面するさまざまな課題と向き合い、乗り越え、人として大きく成長すること、そして、語学や学びたい分野への学習意欲を高めることにある。
期間中に自分の眼で見て肌で感じる「互いの違いを知る驚きと喜び」や「経験のないスケール感」、あるいは「考えたこともない桁外れの現実」は、感受性豊かな中学・高校生に「建設的な破壊」をもたらす。そしてその破壊力は、「自ら考え、自ら学ぶ」ための原動力に変わる。
つまり海外プログラムは、コミュニケーションツールとしての語学や、自分が学びたい分野への学習意欲に火をつけ、そのモチベーションを維持するためにある。「現地で学ぶ」こともさることながら、「日本での日々の学びをより深く豊かにする」ための「気づきの場」なのだ。
現地の生徒やホストファミリーとのかけがえのない時間
設立当初から「世界とつながる学校」
真の誇りは、足で築いたネットワーク
ノートルダム女学院が、これだけ多彩なプログラムを設定できる理由は、「ノートルダム教育修道女会(School Sisters of Notre Dame/以下SSNDと表記)」にある。そもそもノートルダム女学院は、学校設立当初より「世界とつながっている学校」である。
■ SSNDの歴史
| 1833年 |
マザーテレジア・ゲルハルディンガーが、南ドイツ・ババリア地方にてノートルダム教育修道女会を設立し、当時なおざりにされていた庶民の子どもたちの教育、とりわけ女子教育に取り組み始める |
| 1847年 |
ドイツ移民の子どもの教育を求められて4人のシスターたちを連れて渡米。現地の求めに応え、ドイツばかりでなく、あらゆる国の子どもの教育を北米各地で開始 |
| 1948年 |
日本の教会から「敗戦直後の疲弊・混乱する日本には、普遍的な価値観を教える女子校が必要」との要請に応え、アメリカ・セントルイスから4人のシスターが京都に派遣される
 |
| 1952年 |
ノートルダム女学院中学校 開校 |
| 1953年 |
ノートルダム女学院高等学校 開校 |
| 1954年 |
ノートルダム学院小学校 開校 |
| 1961年 |
京都ノートルダム女子大学 開設 |
| 現在 |
同じ精神のもとに、世界の30数カ国で教育活動を展開 |
校長・栗本はこう話す。
「私たちはSSNDのネットワークを最大限に活用しながら、多くの国の学校や生徒と交流してきました。北米なら、本校はもともと戦後アメリカからやってきたシスター方によって設立された学校であり、設立以来、互いに行き来しあうような、非常に密につながっている学校があります。ヨーロッパでは、ドイツ・ミュンヘンにも行きました。2018年にはオーストリア・ウィーンの学校とSDGsをテーマにしたプロジェクトを組み、現地で合同研究発表会を行ったりしました」。
「もちろんそのネットワーク力は誇りの一つですが、私たちが真に誇るべきは、『一つひとつのプログラムを私たち自身でつくってきたこと』です。留学斡旋企業だけに頼らず、私たち自身で学校を選び、現地に足を運び、先方の教員・スタッフと喧々諤々の議論をして学習テーマを設定し、効果的な日程を組んで生徒を現地に送ってきた。注いだ情熱と時間の蓄積の結果、お互いは深い信頼と強い絆で結ばれています」。
海外プログラムの目的は2つ
「違い」を知ること、「自分の枠」を壊すこと
ノートルダム女学院が海外プログラムに注力してきた目的は、大きく2つある。
1)現地に赴き、暮らしに根づく文化や価値観を「生」で感じ、日本との違いを認識する
《代表的なプログラム》
●3カ月留学プログラム
現地で生活しながら、現地の学校に通い、ともに学び、ともに生活をして、違う価値観をぶつけ合う実体験を重ねる。そうした生活環境に身を置くことで、コミュニケーションツールとなる英語力も集中的に鍛える
英語で学び、考え、伝え、語学力に磨きをかける
2)れまでの自分の「常識」や「枠」を壊し、より大きな視野・視界を持つ
《代表的なプログラム》
●フィリピン社会活動ワークショップ
フィリピンを訪ね、貧困や虐待、性暴力などに苦しむ現地の少年・少女たちと交流。日本では考えられない現実を目の当たりにし、「いま、自分はどんな行動を起こすべきか?」を考える。認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパンの協力を得て開発したオリジナルプログラム
現地を訪れ交流のなかから、自分にできることを考える
●ハワイアースサイエンス研修
ハワイ島で、科学、数学界で世界的に活躍する研究者の講義を受講し、キラウエア火山やすばる天文台を訪問。オアフ島では、ハワイ大学の学生をはじめ、地元の学生と交流し、各自が取り組んできた一年間の探究活動の成果を英語で発表
<ノートルダム女学院が築いてきたもの>
圧倒的な現実を目の前にして、
自分の常識や枠を「建設的に破壊」する
数ある海外プログラムのなかでも、とりわけ象徴的なものが、「フィリピン社会活動ワークショップ」だ。
■ 2018年度 フィリピン社会活動ワークショップ
対象:グローバル英語コース 高校2年生
実施日:2019年2月11日~2月17日
| 日程 |
ワークショップ内容 |
| 初日 |
09:55 関西空港出発
13:55 マニラ空港到着
⇒到着後、オロンガポ市・プレダ基金へ移動
《オロンガポ市・プレダ基金内ゲストハウス 宿泊》 |
| 2日目 |
10:00 プレダ基金にてオリエンテーション
⇒子ども支援、貧困解消活動やフェアトレード事業について活動概要のレクチャーを受ける
13:00 虐待から救出された少女たちと交流
《オロンガポ市・プレダ基金内ゲストハウス 宿泊》 |
| 3日目 |
08:30 先住民族のコミュニティへ移動
⇒村の小学校を訪問し、子どもたちと交流
《オロンガポ市・プレダ基金内ゲストハウス 宿泊》 |
| 4日目 |
09:00 路上や刑務所から救出された少年たちと交流
14:00 マニラへ移動
《マニラ市・ホテル 宿泊》 |
| 5日目 |
10:00 国際協力機構(JICA)フィリピンを訪問
⇒現地でソーシャルビジネスとして展開されている日本食レストランを見学・昼食
13:30 市内の歴史的建造物等を訪問・見学
《マニラ市・ホテル 宿泊》 |
| 6日目 |
午前 スラム地域へ移動
⇒現地で暮らす家庭を訪ね、ファミリーと交流。その家庭内で昼食
《マニラ市・ホテル 宿泊》 |
| 7日目 |
14:25 マニラ空港出発
19:15 関西国際空港着 到着後解散 |
ともに時間を過ごすなかで、生徒は気づきや発見を経験
このワークショップの狙いを、グローバル英語コース長・中村はこう語る。
「グローバル英語コースの授業づくりの最大のポイントは、『生徒が本気になれるか?』です。たとえばSDGs。いまやSDGsを学ばない学校はないでしょう。でもこのSDGs、本気で考えさせないと『とても浅はかなもの』になってしまいます」。
「たとえば、17あるSDGsのテーマの一つ目「貧困をなくそう」。いわゆる貧困問題を授業で取り上げるとする。先生が『みんなで調べ学習して、ディスカッションしましょう。その人のために自分は何ができるかを考えましょう。では発表してください』と言う。生徒は『豊かな国が、貧しい国にもっとお金を送ったらいいと思います』というような発表をする。これ、全然本気じゃないですよね。「やってる感」はあるかもしれませんが、極めて表層的で、実感を伴わない、いわば何も学べない授業です」。
現地に足を運び、全身で感じる
そこから「覚醒」が始まる
では、どうすれば生徒を本気にさせられるのか? その答えのひとつが「現地に足を運んで全身で感じること」だと中村はいう。
「実際にフィリピンに行ったら、想像をはるかに超える貧困、人が人として尊ばれていない現実が目の前に広がっている。私自身も『これヤバいよなぁ・・・』とか、『こんなん絶対おかしい』とか、鳥肌が立つぐらいに感じた。俗っぽい言葉で申し訳ないですが、言い表わす言葉を思いつく間もなく、次から次へと驚くような現実が目の前に現れ、本当に言葉を失いました」。
「生徒たちもそうでした。普段はふざけ合ってはしゃぎ回る生徒たちが、夜みんなで集まって『私たちはいったい何ができるんやろうな…』と、深刻な顔をして話し合っていた。豊かな日本の、さらに一番安全な教室の中で語り合うだけでは感じられない恐怖や絶望感。その中にありながらも、何かをたぐり寄せたくなる心の渇きと怒り。衝撃的な現実にさらされ、おのずと本気になる。今まで自分に見えていた景色はごく限られた世界だった、何も知らなかった。そこに気づいてはじめて、覚醒が生まれます。フィリピンに行く意味はそこにあったんです」。
<今後の海外プログラムあり方>
国を超えたバーチャル教室など
ICTを活用した環境づくりも視野に
海外での体験を取り入れたプログラムを構築し、実際にそれを体験した生徒たちが大きく変容するのを目の当たりにしていた2020年。突如として世界を襲った、新型コロナウイルス。おそらくしばらくは渡航できず、それは数年に及ぶ可能性も高い。では、今後海外プログラムは諦めるしかないのか? ICTを活用した『バーチャル留学』などの可能性は考えられないのか?
ICT化の推進役を担う教頭・鳥山はこう語る。
「どこまでを視野に入れるのか、その見極めが必要です。他国の学生とSDGsのテーマについて語り合うといった授業は、毎日できるテーマではありません。できたとしても、週1回程度です。この程度の頻度ならZoomでもできます。真の留学レベルの効果を得たいなら、英語も数学などの教科も現地の生徒と一緒にオンラインで受講するレベルにまで密度を高めることが必要です。そのためには、日本と海外、2つの教室をオンラインでつないでバーチャル教室をつくることも検討しなきゃいけない。なかなかそこまで一足飛びにはできません。とはいえ、いま海外へ出向くことは事実上不可能です。とすればやはり、そうしたインフラを整えることも視野に入れておかねばならないと思います」。
栗本は、こうまとめた。
「現地(場)の力は絶大です。図書館で調べるより、肌や脳に沁み込む情報や胸に刻まれる熱があります。ですが、日々の授業でそうしたものばかりを扱うこともできません。ならば、この京都・鹿ケ谷にいながらヨーロッパやアメリカ、アジアの学校とつながり続けられる仕組みを模索する。日常的でsustainableに海外体験できるインフラを整えることは、今後、避けては通れない大きな課題です」。
<今後の海外プログラムのあり方>
今後意識しておくべき
コンテンツづくりの「3つ」の方向性
しかし、インフラ整備自体は課題解決の第一歩に過ぎない。突き詰めれば、そのインフラを活用して何をどう学ばせるのか?というコンテンツの良し悪しが問われることになる。栗本はコンテンツづくりの向かうべきところを、こう示唆する。
「今後は、ノートルダム女学院が背骨とするSSNDネットワークと、私たち自身がプログラムづくりを通じて培ってきた他国の学校との絆の真価が問われます。今後のコンテンツづくりで意識しておきたいことは、次の『3つ』だと考えています」。
その3つとは、
- ① 「アジアの中の自分」を意識できるプログラムづくり
- ② 非日常性と自分の限界に挑戦する環境づくり
- ③ 「自己」と「他者」が交わり合う場づくり
だ、栗本は言う。
① 「アジアの中の自分」を意識できるプログラムづくり
「1948年にアメリカ・セントルイスから4人のシスターが京都に派遣され、1952年にノートルダム女学院中学校が開校されました。間もなく70周年を迎えます。カトリックの教えに基づくノートルダム女学院の教育は、言うまでもなく、欧米の英語文化圏の教育メソッドです。だからこそSSNDのネットワークが活きるし、それは私たちのLegacyそのものです。が、21世紀はアジア太平洋の時代です。欧米だけを見続けてはいけない。なぜなら、私たちはアジアに暮らす人間だからです」。
栗本は、従来のノートルダム女学院では意識されにくかった「アジアを意識した教育」を語る。
「2019年12月、私は、日本のSSNDがネパールにつくった学校を視察するために、現地に足を運びました。日本のSSND設立は1948年です。そこからさらに35年経った1983年、日本からネパールに4人のシスターが派遣され、1985年にその学校が設立されました」。
「当時のネパールの識字率(15歳以上で母語の読み書きできる人の割合)は10%足らず。高度成長期を経て、日本は豊かな国になりました。他国の人々の援助で成長できた私たちも、同様に他国の教育に協力したい。その思いから始めた、日本人修道者によるネパールでの学校づくりです」。
ネパール・バンデプールの学校にて
「アジアに生きる一員として、欧米だけではなくアジアを強く意識し、「世界の中のアジア・アジアの中の私」に誇りをもつ。その意義を生徒たちに伝えられる海外プログラムをつくりたい。ネパールにある私たちにとって一番身近なお手本を、この眼で確かめたい。それが、私がネパールを訪ねた理由でした」。
「残念ながら、いまのこのコロナ禍では、ネパールへの渡航はできません。しかし、私たちにはすでに、中国、韓国、台湾、グアムなど、アジア各国・地域にネットワークを持っています。まだまだ暗中模索ですが、それが活かせる『世界の中のアジア、アジアの中の日本』を意識できるプログラムをつくりたいと考えています」。
アジアを意識し、アジア人であることに誇りを持つプログラムづくり
② 非日常性と自分の限界に挑戦する環境づくり
「たとえ海外という大きな舞台装置を失ったとしても、生徒を本気にさせるために打つ手は絶対にあるはず。環境を整えることはできると思うんです」。
グローバル英語コースの責任者である中村は、意志を込めてそう語る。中村は、これまでにも生徒向けに多くのワークショップをつくり、指導にあたって来た。
「関西学院大学の關谷武司教授のご指導をいただき、2017年から毎年、国際情報分析ワークショップを行っています。関西学院大学キャンパス内の教室で行われる、2日間のワークショップです。世界情勢に関する時事問題を取り上げ、情報収集と情報分析を集中的に行う。いわゆる『調べ学習』とは次元が異なる、大変高度な研修プログラムです。もちろん、海外なんて行きません。けれど、この研修に参加する生徒たちは間違いなく本気です」。
その理由を中村はこう分析する。
「そこにはやはり、本気にさせる仕掛けがある。まず何よりも、大学のキャンパスや図書館といった大きな場の力が、生徒の意識に作用しています。中学・高校生にはまぶしいほどのアカデミックな空間に身を置きながら、学問に触れる。その非日常感は刺激になっています」。
そして、もう一つの大きな力も作用しているという。
「それは『自分の限界に挑戦する環境』です。あしたの朝には必ず発表しないといけない、それまでにはみんなでレポートをまとめ上げねばならない、という厳しいデッドラインが設定されている。ジリジリ・ヒリヒリするような『〆切意識』です。膨大な情報と迫りくる期限を目の前にして、寝る間も休む間も惜しみながら、チームが力を合わせて取り組む。どの生徒も、まさに本気です。ふだんの教室を離れた非日常的な空間と『自分の限界に挑戦する環境』。その二つに加え、いろんな仕掛けが巧みに織り込まれたプログラムで、生徒たちの本気度はまったく変わってきます」。
本気で取り組むことを学ぶ關谷教授のワークショップ
③ 「自己」と「他者」が交わり合う場づくり
3つ目は、「この人のためにある私」という当事者意識を持たせること、と栗本が継ぐ。
「実際に足を運ぶ前、生徒たちは『スラム街は怖い。汚いし、臭い』、口には出さずとも『本当に行くの?』と思う生徒もいた。その生徒たちが、子どもたちと一緒に話して走って笑って・・・。お昼ご飯も「コレ食べて大丈夫なん?」とあやしみながらも、チキンスープを食べさせてもらって。おそるおそるスープを口にしてみると、『え?おいしい!もしかしてこれ、おいしいよね!』と笑顔になって子どもたちともたくさん話し、夢を語り合った。帰る間際、お母さんから片言の英語で「Come back!」と言われ、『もう一回来たくても、番地もない・・・』と泣き笑いして。最後は涙、涙で家族の一人ひとりに何度も何度もハグして別れた」。
「人と人、自分と誰か。心底、この人と通じ合えた思える瞬間を経験した。そんな濃密な時間を共有するなかで、自分の住む日本と、そのスラムとの間にあるギャップに疑問を持ち始める。こんな世界はおかしい、何かが間違っている!と考え始めた。それもこれも、自分の目の前に愛おしいと感じられる人がいるからです」。
「あの現場に流れた、パーソナルで濃密な時間をつくること。私とこの人はつながっている、だから放っておけない。一刻も早く動き始めないと大切な人が困る。その湧き上がる思いが学びに向かう源泉になります」。
「生徒を本気にさせるには、『ワンタイム・イベントに終わらせない』こと。大切な人とつながり続けられる環境をつくる。つながっていれば離れがたい人間関係が育まれ、おのずと本気度も高まっていく。そうした心のコンディションが整う環境をつくることが大切です」。
濃密な時間を経て、社会課題に対する当事者意識が芽生える