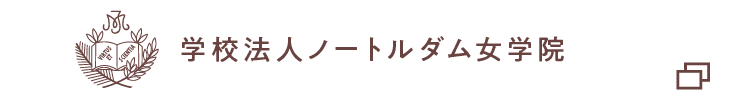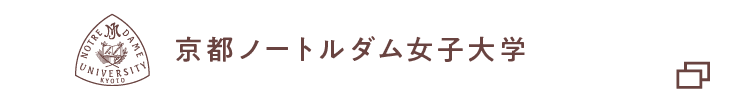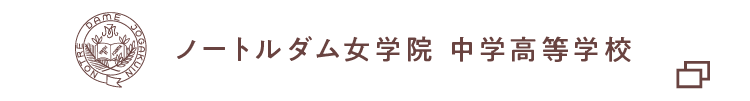ノートルダム女学院では、中学1〜3年生を対象として、「言語技術」という特別授業を行っている。この授業は言語運用能力、論理的思考力、批判的思考力(クリティカルシンキング)を身につけることを目的としており、一般的な「国語」の授業とは性格が異なる。
この授業を担当する北村昌江と水野有紀に導入の狙いと効果を聞いた。
担当教員

(左)言語技術科 北村昌江
(右)社会科・言語技術科 水野有紀


欧米とは異なる日本語教育の思想が
グローバル時代の相互理解を阻む?
「言語技術」とは、 欧米圏の母語教育「Language Arts」の日本語訳である。この「Arts」は、Liberal Artsの「Arts」と同じく、「人が社会的な営みを続けるために必要な技芸・学芸」を意味する。英語が母語の人なら、不都合なく社会生活を送れるように英語を学ぶためのメソッドである。
それだけ聞けば、日本人には「国語」があり、ことさら「言語技術」を学ぶ必要はないとも思えるが、そうではない。長年、初等・中等教育の現場で国語の授業に携わってきた北村は、その違いについてこう解説する。
「そもそも日本と欧米では、母語教育に対する基本姿勢が異なります。日本の国語の授業は、文章を読んで内容を理解し、登場人物の心情を察することなどに重きを置いた『共感的教育』です。『おーい、あそこに置いたアレ、頃合い見て適当に持ってきて!』。日本ならこんな会話も成り立ちます。まさに『忖度できる国民性』ですね。一方で欧米の母語教育で重視されるのは『論理的教育』、言い換えれば、思考力や問題を解決できる力です。おーいは誰(Who)? あそこはどこ(Where)? あれは何(What)? 頃合いはいつ(When)? 適当にってどうやって(How)? なぜ(Why)? 何のために(What for)? これらが明確に示されなければ、会話が成りたちません」。
言語技術は、言語の運用能力、論理的思考力、批判的思考力(クリティカルシンキング)を身につけることを目的として、体系的なプログラムが構成されている(上図参照)。

「まずは、論理的思考の基礎となる問答法や、情報が事実か意見かを区別する練習、自分の考えを論理的に文章で表現する世界標準の書き方・パラグラフライティングを学ぶことから始まります。『情報伝達』『情報分析』『多面的な視点で考える』などのワークをはじめ、『ディスカッションの仕方』『小論文の書き方』なども学び、最終的には自分の意見を発表する『プレゼンテーション』へとまとめ上げていきます」。
このトレーニングの中でも、とりわけ生徒のテンションが高まる教材が、冒頭に掲げたような絵や文章の分析だ。 「絵の分析では、絵の全体と部分から得られるfact(事実)に基づいて、論理的に自分の意見を組み立てていく力を鍛えます。たとえばゴッホの名画分析では、場所はどこか? 時間帯はいつか? 糸杉は何を意味しているか? 空の星や月は何を表現しようとしているか? などについて根拠をもとに読み解いていきます。生徒の分析は、『ヨーロッパの高台にある精神病院から見た風景で、黒く揺らめきながら空に伸びる糸杉は、ゴッホ自身が天に昇る死の予感であり、夜の空の星や月の歪みは、ゴッホの不安定な心理状態を示している』というもので、大人顔負けの分析をしていました」。

「最近で一番盛り上がったのは、往年のヒット曲『木綿のハンカチーフ』の歌詞の文章分析です。4番の歌詞に至るまでに、主人公の男性には何が起こったと推察されるか? その時、彼女の彼に対する気持ちにはどんな変化が起きたと思われるか? それはなぜか? 歌をよく知る大人では思いもつかない、新鮮な切り口からの分析や推論が出ましたよ」。
暗記中心になりがちな社会科科目が
自分の意見を述べ合う討議型授業に!
この授業の効果を実感する一人が、社会科を担当する水野だ。水野は、北村が持つ指導ノウハウを、学内のナレッジとして標準化する役割も担っている。
「たとえば社会科なら、地理の授業の質が変わりました。ともすれば暗記に陥りがちな科目ですが、それでは地理を学ぶ意味は半減します。地図や各種の統計、年代ごとに残されている記録写真などから、その地の気候、政治、経済、さらには民族・民俗性や文化環境までをひも解く。それらを論拠に、地域の課題解決や活性化のアイデアを議論する。そうすれば、本来の目的に近づくことができます」。
「1年生のときには人前で話すことすらしどろもどろだった生徒が、3年次には自分の意見を大胆にプレゼンテーションし、うろたえることなく質疑も受けて立てるようになる。成長したなぁ……と実感する瞬間ですね」。