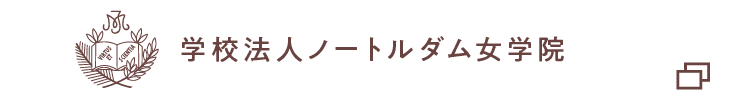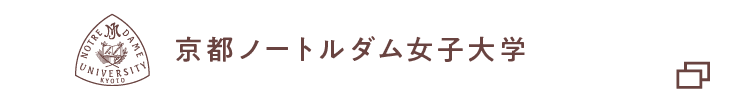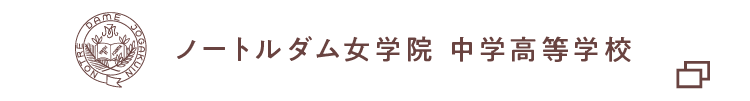70年前のシスターの意志を継ぎ
ノートルダム教育の原点に返る
栗本お話を聞いて、あらためてノートルダム教育の原点に立ち返る思いがしまています。1948年、アメリカ・セントルイスから4人のシスターが、ほんの数年前までは銃を向け合った敵国・日本の京都に学校をつくりにやってこられた。キリスト教の普遍的な価値観に基づいて、自らに与えられた命を誰かのためにつかう、そのような心を自分の中心に据えている女性を育成することこそが日本を開き、未来につながる原動力となる。そう信じて遥かな海を渡ってきた。実は彼女たちこそ真にグローバルな人々であり、彼女たちが創立した本学院は、まさに初めから「グローバルな学校」でした。
中村京都ノートルダム女子大学は、服飾や調理・栄養の専門学校を前身とする女子大学とは多少事情が異なります。1952年のノートルダム女学院中学校開校、翌年の高等学校開校を経て、中学・高校の卒業生、在校生や家族からの要請を請け、1961年にその進学先として設立されました。専門学校的な技術や知識の修得が目的ではなく、もともとリベラルアーツ的な大学なのです。女性キャリアデザイン学環は、本学の設立経緯や教育方針を集約させた教育組織といえます。
栗本お話を聞いて、あらためてノートルダム教育の原点に立ち返る思いがしまています。1948年、アメリカ・セントルイスから4人のシスターが、ほんの数年前までは銃を向け合った敵国・日本の京都に学校をつくりにやってこられた。キリスト教の普遍的な価値観に基づいて、自らに与えられた命を誰かのためにつかう、そのような心を自分の中心に据えている女性を育成することこそが日本を開き、未来につながる原動力となる。そう信じて遥かな海を渡ってきた。実は彼女たちこそ真にグローバルな人々であり、彼女たちが創立した本学院は、まさに初めから「グローバルな学校」でした。
中村京都ノートルダム女子大学は、服飾や調理・栄養の専門学校を前身とする女子大学とは多少事情が異なります。1952年のノートルダム女学院中学校開校、翌年の高等学校開校を経て、中学・高校の卒業生、在校生や家族からの要請を請け、1961年にその進学先として設立されました。専門学校的な技術や知識の修得が目的ではなく、もともとリベラルアーツ的な大学なのです。女性キャリアデザイン学環は、本学の設立経緯や教育方針を集約させた教育組織といえます。
女性がトップの中・高・大
さらなる接続プログラムをつくりたい
栗本ノートルダム女学院のミッションコミットメントは、「尊ぶ(Respect)・対話する(Dialogue)・共感する(Empathy)・行動する(Action)」。人が人に接する際に必要となる基本的で普遍的な心を4つの動詞で表しています。この4つは、男女や時代を問わず、リーダーに求められる資質です。先ほど「少人数制が大切」というお話がありましたが、小学校、中学・高校、大学のいずれを問わず、ノートルダム女学院では「教員と生徒・学生との距離の近さ」を大切にしています。言うならば、キャンパス内には、いつも互いを尊び、対話し、共感し、行動できる環境が整っています。これこそが私たちのめざす教育です。
【ノートルダムのミッション】

中村もう一つお話しておけば、これだけ中学・高校と大学の距離が近い学校も少ないと思いますよ。今日もこうして学校長と学長が気軽に気さくにお話できます。俯瞰すれば、女子大学でも学長は男性が務められているケースが大半です。
栗本中学・高校も同じで、京都府の女子校で女性が学校長を務めるのは、1割もありません。ましてや同じ学校法人内で、中学・高校と大学ともに女性がトップで指揮を執る学校となると、全国的にも珍しいと思いますね。
中村すでに、中高大接続プログラムがいくつも行われています。高大連携プログラム[みらいデザイン☆ハイスクール]もその一つです。これからも一層、「女性のライフキャリア設計」支援に向けて、さまざまな連携プログラムを一緒に開発していきたいですよね。
栗本ぜひ、これからもよろしくお願いします。
高大連携プログラムみらいデザイン☆ハイスクール
高校時代にこそ、未来を考える機会を高大連携で未来を考えるワークショップを開催
ノートルダム女学院・プレップ総合コースでは、“私らしい未来を見つける“というコンセプトのもと、高校3年間にわたる授業「フューチャー・プロジェクト」を展開している。その中の1つのカリキュラムとして、毎年秋には高校2年生向けに「みらいデザイン☆ハイスクール」を開催。さまざまな学部に進学した大学生や多彩な職業に就く社会人ゲストから、ありのままの生き方や価値観を聞くことができる場が設けられている。
これは、京都ノートルダム女子大学・キャリア形成ゼミの1つ、ワークショップ・デザインゼミ(ND教育センター・濱中倫秀准教授)と連携した高大連携プログラム。濱中准教授指導のもと、ゼミ生たちが、企画・ゲスト選定・依頼交渉・当日設営などのすべてを統括・運営する。
高校生にとっては、半歩先ゆく大学生や、やりがいを感じながら学び働く社会人の先輩たちと接し、等身大の刺激を受ける場となる。と同時に、ゼミ生にとっても、リーダーシップ/フォロワーシップを持って、すべてを取り仕切る経験の場にもなっている。高校生・大学生両者にとっての「Win-Win」が成立した高大連携プログラムだ。
 例年、ゲストは約10名。それぞれのテーブルにつき、少人数でじっくり話を聞く
例年、ゲストは約10名。それぞれのテーブルにつき、少人数でじっくり話を聞く
 濱中倫秀准教授と「ワークショップ・デザインゼミ」受講生
濱中倫秀准教授と「ワークショップ・デザインゼミ」受講生