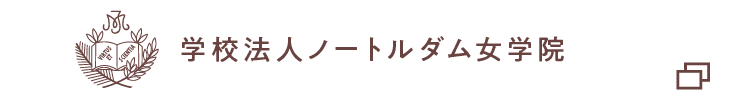ノートルダム女学院では、教育界をはじめ、経済界、行政、地域など、多くの皆様の理解と協力をいただきながら独創的な教育プログラムを展開しています。
この「X-CROSS TALK」では、学校長・栗本嘉子が「ノートルダム女学院流の教育」について、各界の専門家とともに語り合います。
今回のゲストには、ノートルダム女学院OGでもある教育ジャーナリスト・加藤紀子さんをお迎えしました。
良い子育て・良い学校は「子どもが主体」
栗本著書「子育てベスト100」を拝読しました。親が感じる疑問や不安など、痒いところに手が届いたテーマ設定、学術的エビデンスと経験にもとづいた解説、具体的なアドバイスが満載で感服しました。
せっかくの機会ですから、ズバリお聞きします。教育ジャーナリストの加藤さんの眼から見て、「良い子育て・良い学校」とは、どのようなものだとお考えですか?
加藤藤「子どもが主体」であること、これに尽きると思います。それは家庭での子育ても学校の教育も同じです。子どもが主体の環境とは、「子ども自身が今日を幸せだと感じ、明日を楽しみにできる場」です。小さい時期ほど、心から今日は楽しかったと思えることが大切です。
栗本自主性を尊重するということですね。それは「甘やかし」と何が違うか、わかりやすく言うと?
加藤自主性の尊重と「甘やかし」との違いは、何でも子どもの言いなりになるかどうかです。宿題やお手伝いなどやるべきことをなおざりにしてゲームばかりやっているのを放っておくのは「甘やかし」。自主性の尊重とは、子どもの気持ちに耳を傾けつつ、親としての期待や心配事を伝えるために親子で対話をすることです。加えて、いつも親が子どもを先導し、「将来役に立つから」と親が決めた課題ばかり押しつけて、子どもが今やりたいと望んでいることを後回しにするのも自主性の尊重とは言えません。そんな状態が続けば、子どもが生きることへの無力感にとりつかれてしまいます。
栗本子どもに芽吹いた興味を、親が自ら摘み取っているかもしれないですね。
加藤ともすれば親は、自分の価値観や経験をもとに子どもに話をしてしまいがちです。そして、私自身もそうでしたが、「子どものため」と思ってやっていることの中には、実は「親が安心する」だけのためではないかと思えるものが多いんですよね。
栗本教師も同じです。特に教師は「教えたがり」な傾向にあります。質問されたこと以上に先回りしたくなる。「そこではきっとこんなことが起こるけど、こうすればウマくいくよ」。それじゃ未知に出会う驚きも感動も半減します。それは「コーチング」ではなく、「コントロール」です。
加藤自分の子どもであっても、子どもなりの感情や意思があります。興味のアンテナが向く角度も違えば、反応する感度も違う。もっと知りたい、できるようになりたい。その対象はもちろん勉強でもいいし、スポーツでも音楽でも構わない。そのパッション(情熱)を応援してあげたら、いつの間にかそれが積み上がって、みんなよりいっぱい知っている、できるようになる。これが自己肯定感や自信につながっていきます。
栗本「子どもが主体」とは、親や教師が子どもに芽生えた好奇心やワクワクする気持ちに伴走してあげること。それがワガママなのかどうかは、その興味や思いの強さを見極められるかどうか。親や教師の判断力が問われているのですよね。

鳥の眼・虫の眼・魚の眼
栗本加藤さんの「教育ジャーナリスト」というお仕事にも興味を惹かれました。親と子ども、教師と生徒のコミュニケーションは、基本的に「向かい合う視線」です。著書を読み終えて、教育ジャーナリストは、その直線的・対極的な関係を俯瞰してみる眼、第三者の眼を持ち込むことができる仕事なんだ、と。
加藤実は私も「教育ジャーナリスト」の何たるかは、まだよく自覚できていないんですけど(笑)。ただ、私が書き物をする際には、「3つの眼」を大切にしています。
栗本「3つの眼」?
加藤「鳥の眼・虫の眼・魚の眼」です。
まずは「鳥の眼」。教育と社会は地続きなので、教育だけに限定せずもっと広い視点からとらえること。そのためには、時々ビジネス関連の記事を書いたり、さまざまな職業の人と交流したりする時間も大切にしています。
次が「虫の眼」。真実は現場にしかないので、リアルな現場を取材すること。
最後は「魚の眼」、文字通りの魚眼です。片方では社会で起きている出来事や最先端の研究を知り、片方では現実を見る。その二つをつなぎ、進むべき流れを見定めることです。
栗本教師は教育現場の人間ですから、虫の眼で見がちです。もちろん、広い視野や大局観を持って変えていきたいという情熱はあります。でも何かを変えるには、少なからずリスクも伴う。そのせめぎ合いもあって、道を曲がろうにも急には曲がれません。自ずと車輪は重くなる。
教育理論と教育現場に精通し、今後の教育のあり方を示唆し、それを私たちにわかりやすく伝えていただける「翻訳家」になっていただければ心強いです。
ノートルダム流
「グローバル教育」とは?
栗本今年、ノートルダム女学院は創立70周年を迎えました。そして私が学校長になってちょうど10年が経ちます。この10年間、私なりに「ノートルダム女学院ならでは」の教育を求めて、さまざまな変革を行ってきました。加藤さんは本校の卒業生でもありますよね。その眼から見た、いまのノートルダム女学院の印象をお聞かせください。
加藤私の時代とはずいぶん変わったな、と。ただしそれは、ノートルダム女学院に限らず、時代や社会の要請に応じて多くの学校でも同様に変わりました。たとえばこの10年間、どこの学校でも「グローバル」「リーダーシップ」「探究」といった言葉を使った教育方針を掲げるようになりました。逆に私がお聞きしたいのですが、「ノートルダム女学院ならでは」という思いはどこに込めていらっしゃるのですか?
栗本たとえば「グローバル」という言葉は、私たちも使っています。でもふと冷静に考えれば、あらためて掲げるまでもなく、ノートルダム女学院は初めからグローバルでした。太平洋戦争後の混乱の最中、日本からの要請に応え、4人のシスターがセントルイスから海を渡りました。セントラルヒーティングの国・アメリカから火鉢の国・日本へ。この京都・鹿ケ谷に学校を開いた4人のシスターたちの情熱こそ、私たちの原点です。ならば、その意志とカトリックの教えに立ち返り、私たちにしかできないグローバル教育を目指すべきだ、と。
加藤英語力やリーダーシップ、探究力が身につくといった、聞こえのいい言葉だけに頼らない教育ですね?
栗本はい。人を思う、誰かのためにある自分の存在に気づく。それこそが私たちらしいグローバル教育なんじゃないか、と。
いろんな海外留学プログラムも開発しました。もちろん、英語力を高めるためのイギリスや北米・カナダへの留学もあります。ノートルダムの発祥国・ドイツに出向き、現地の生徒たちとSDGsについてディスカッションするプログラムもつくりました。これらは、世界に拡がるノートルダムのグローバルネットワークがあるからこそのプログラムです。
その中でも、これはノートルダム女学院にしかできないもののひとつに、「フィリピン社会活動ワークショップ」があります。これは、フィリピンのスラム街に生きる少年・少女、その家族とともに過ごし、勉強を教え、遊び、食事をし、かの地を肌で感じる研修です。日本では想像もつかない絶望的貧困、性暴力や虐待を嫌がうえにも目の当たりにします。
研修に行く前には、「なんで危険なスラム街に行かなきゃいけないの?」「汚いのは嫌!」、そんな声をあげる生徒も出ます。でも、研修を終え、ホストマザーにお別れのハグをされると、知らないうちに涙を流している自分に気がつく。キラキラした笑顔でちぎれんばかりに手を振る子どもから「また来てね!」と見送られれば、「必ず戻ってくるね」と唇を噛みしめる。
とある生徒が、町を離れるバスの中でつぶやきました。「私、ウソついちゃった…。できれば、またあそこに還りたい。でも、あそこには電話はおろか、住所も番地もない。先生、私はどうすればまたあの場所にたどり着けるんですか…。こんな不条理な世の中があるんだ…」。そう言って、再びさめざめと涙を流す。

「フィリピン社会活動ワークショップ」の様子。認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパンの協力を得て開発したオリジナルプログラム。貧困、性暴力や虐待などに苦しむ現地の少年・少女たちと交流。日本では考えられない現実を目の当たりにし、「いま、自分はどんな行動を起こすべきか?」を考える(2020~22年はコロナ禍のため中止〈再開未定〉)。
気づきをつなぎ
自分の世界を拡げる
加藤自分の価値観や既成概念を覆す研修ですね。自分が暮らす以外の場所には、これほどまでの不条理や理不尽が満ちているのか。その人たちの現実を目の当たりにし、何かがおかしいという憤りで心が軋む。
栗本SDGsの1番は「貧困をなくそう」です。これをどう学習しましょうか?「豊かな国が貧しい国にお金を支援すればいい」。そんな表層的な結論を出したところで、何の学びにもつながりません。
「私はあそこに還らなきゃ」。使命感にも似た衝動が全身に充満する中、悶え、考え抜く。果たしていまの「私」は、あの人たちにいったい何ができるのか?初めて心の中に小さな灯火がともる。
聖書の言葉、「隣人を自分のように愛しなさい」。これこそが、ノートルダム女学院流のグローバル教育だと思うんです。
加藤感情を揺さぶられる体験を経て、これまで気づかなかった「隣人」の存在を知る、ということですね。
栗本そう。その人には父や母、兄弟・姉妹がいる。その家族には日々を過ごす町があり、その町は隣の地域につながり国となる。さらにその先には複雑な歴史関係を抱える別の国もある…。
小さな、でも本質的な気づきを持って出会った一人の「隣人」。その人を知れば知るほどに心の灯火は大きくなり、家族や町のことまで知りたくなる。やがてそれは、国境や言語の違いすらも飛び越えていく。たとえ一人の「隣人=点」から始まったとしても、つながり続ければ、地球規模での相互理解へと拡がっていく。
加藤私、「グローバル人材」という言葉があまりしっくりこなくて。世界を舞台に活躍する国際人って言われても、フワッとしていて何も伝わってこない。まずは隣の人に気づき、関心を持つこと。そのつながりと拡がりを繰り返した結果で育つのが、カトリックでいう“For others”の精神であり、真のグローバルな感性を持った人なのではないでしょうか。その点で、ノートルダム女学院ならではの「グローバル」には奥行きを感じます。
コンフォートゾーンから抜け出そう
加藤いまのお話を聞いてあらためて、「自分を知る」ことの大切さを感じました。自分の環境や自分自身を客観的に評価でき、そのありがたさに感謝できてはじめて、相手の置かれた境遇や痛みを肌身で感じられるようになります。そのためにも、日常的な心地よい空間やコミュニティ、「コンフォートゾーン」を脱け出してほしいです。特に多感な中学・高校時代にこそ未知の世界に飛び込んだほうがいい。その原体験が将来、多様な人々と支え合って生きていく力の土台になっていくはずです。
栗本「隣人愛」は誰もが知る言葉ですが、本当の意味で隣人愛を生きるのは簡単ではありません。聖書には、「良きサマリア人」の話があります。イエスが「愛するとはどういうことか」を端的に教えるもので、実に示唆に富んでいます。彼は旅人で、日常とは異なる毎日を生きています。過酷な旅にあってなお、助けが必要な人と出会えば、惜しみなく自分のエネルギー、時間、お金を注ぎ込み、痛みを伴う行動を重ねて「隣人」になっていくのです。
学校の中は、ある意味コンフォートゾーンです。でも、皆いつかはそこを完全に抜け出して旅に出ます。抜け出た先で、どのような生き方をしていくのか? カトリック学校として、そこはきちんと教えて行く必要があります。ここで過ごす間に、少しずつ小さな体験を積み重ねて隣人愛に生きること、つまり真剣に自分がだれかの隣人になっていくことを学んでほしいと願っています。
加藤自分の未来を見つめる力、自分で切り拓く力を身につけるということですね。
まさにそれは、進路選びにも通じる視点だと思います。初めから目標ややりたいことを明確に設定できている生徒はそういません。だからこそ、どんどん回り道すればいいし、迷えばいいと思うんです。いろんな角度にアンテナを向け、そこに引っかかったものに反応し、進んでみてはまた戻り。そうやって右往左往しながら気づいたらいくつもの点がつながり、自分らしさが育まれていく。それが人としての成長なのではないでしょうか。
安心して「手探り」を楽しめる学校に
栗本その時学校がすべきことは、逆説的ですがコンフォートゾーンをつくる、つまり「安心して迷える場、手探りを楽しめる環境を整える」ことですね。そして機が熟せば、そのコンフォートゾーンから安心して巣立てるよう、背中を押してあげる。
加藤子どもは一人ひとり、興味・関心のベクトルが違います。話をよく聞いてあげて、対話をする。先導するのではなく、伴走する。子どもから学び、自分自身も成長し続ける。それが先生や親の役割だと思います。
栗本まさにそれが「生徒が主体」。そうありたいと思います。ただ残念ながら、私たち教師は万能じゃない。恥ずかしながら知らないことばかりです。ましてや5年後・10年後の予測なんてできやしない。
だからこそ、知らないということを知る「無知の知」が大切です。知らないこと・わからないことはその分野の専門家の力を借りればいい。そうしたネットワークを広げ、正しくアウトソースできる仕組みをつくることも、今後の教育現場の大きな課題です。ぜひ、教育ジャーナリストとしての加藤さんの力もお貸しくださいね。
加藤喜んで。社会に開かれた学校として、ますますのご発展を応援していきたいです。
同じ母校の先輩・後輩でもある二人。互いの在籍当時の恩師や学校行事の思い出話にも花が咲き、対談は2時間半にも及んだ。初対面ながら、一瞬にして本音で語り合えたのも、同じ学舎に学んだ同窓生ならでは。
加藤紀子さん著「『最先端の新常識』×『子どもに一番大事なこと』が1冊で全部丸わかり『子育てベスト100』」(ダイヤモンド社)。コミュニケーションの取り方、家での勉強の仕方、遊び、習い事、ほめ方・叱り方、食事、運動など、子育ての多様なテーマをカバーした「子育ての教科書」。累計17万部を突破。
2022年8月に発刊された2冊目「ちょっと気になる子育ての困りごと解決ブック!」(大和書房)。授業中に立ち歩く、ゲームばかりしている、すぐ手が出てしまうなど、気になるところのある子どもの気持ちや考えを理解して、最適な接し方を伝授。